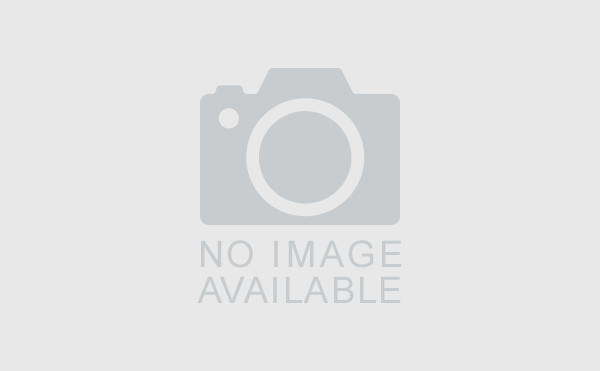小学生読解力の分かれ道
徳島市城東の学習塾「ウィル学習塾」です!
こんにちは。
少人数指導の学習塾「ウィル学習塾」、の十川です。
小学1年生~中学生~高校生が対象の、少人数個別指導&個別授業を組み合わせた学習塾です。
このホームページでは、徳島市、特に城東地区で塾をお探しの方に、学習塾ウィルがどのような塾かをご紹介しております。
ブログでは、私たちの指導への考え方や教室での出来事を書いていきますので、教室の雰囲気が伝わりましたら幸いです!
それでは、本日は小学生の読解力の上げ方についてのお話をします。
教科書に取り上げられている
かえるくんとがまくんのお話です。
かえるくんとがまくんは親友です、ややこしい笑
来ない手紙をずっと待っているがまくんに、
かえるくんは自分で手紙を書いて、かたつむりくんに届けてくれるよう頼みます。
(なんで、かたつむりくんみたいなゆっくりした奴に頼むのか、というつっこみは、どんどんしてください)
さみしそうに外を眺めながら
「手紙なんか、こやしないよ」と言うがまくんに、
かえるくんは、「きっとくるよ。だって、ぼくがきみにお手紙を書いたんだもの」と言うのです。
・・・・・・・・・・・・・・・
さて、問題です。
☆「きっとくるよ」
かえるくんがこう言ったのは、なぜですか?
正解は
「かえるくんが、がまくんに
手紙を書いたから」
なんだ、簡単じゃん、って思うでしょう??
ここには簡単ではない大きな壁があります。
かえるくんが、がまくんに手紙を書いてあげた、という
客観的な事実を、第三者として説明できるようにならないと
この問題に対する答えは書けません。
小学2年生のA子ちゃんは、
「だって、ぼくがきみにお手紙を書いたんだもの」
と答えました。
本文の内容をそのまま写しただけです。
そして、大きなバツをもらって帰ってきました。
この文章の中の「ぼく」が、かえるくんであることを説明できないのです。
本文の中で、このシチュエーションでは
「ぼく」はかえるくん。
「きみ」はがまくん。
それを第三者に説明することが
できないのです。
これは、小学校低学年の子供には
大きな壁なんだと感じました。
でも、解決法はわかります。
絵本をたくさん読んでもらうことです。
自分(本人)が自分で「ぼく」と呼ぶのと、
絵本の世界で主人公が「ぼく」というのとは
違うことを感じるのが大事かと思います。
もしかして(間違えているかもしれないけれど)
これが「抽象化」して考えるということなのかもしれません。
さて、どうやってこの子に
本人の「ぼく」と、かえるくんの「ぼく」が
違うのか、というのを感じ取ってもらおうか、
というのが大きな私の課題です。
※ちなみに、かえるくんが書いた手紙は
4日もかかって、がまくんのもとに
届けられます。
つっこみどころ満載なこの、かえるくんとがまくんのストーリーは
絶賛、本屋で発売されています。
本日も、ありがとうございました!
現在、ウィル学習塾では生徒さんを募集中です。
徳島市で塾をお探しの方、ぜひ一度見学にいらしてください。
お問い合わせはこちらから。
お問い合わせフォーム▶ここをクリック
電話▶088-664-3668
最後に、教室へのアクセスをご紹介しますので、参考にしてみてくださいね!
ウィル学習塾の住所
〒770-0874
徳島県徳島市南沖洲1-2-3
車で来られる方へ
※駐車場6台分あります
小学校からのアクセス
徳島市沖洲小学校:徒歩5分 / 自転車4分 / 車で4分
徳島市福島小学校:徒歩20分 / 自転車15分 / 車で10分
徳島市城東小学校:自転車20分 / 自転車15分/ 車で10分
徳島文理小学校(私立):自転車30分 / 車で15分
中学校からのアクセス
徳島市城東中学校:徒歩5分 / 自転車4分 / 車で3分
徳島市徳島中学校:自転車20分 / 車で10分
徳島市富田中学校:自転車30分 / 車で20分
徳島市津田中学校:自転車30分 / 車で15分
徳島文理中学校(私立):自転車30分 / 車で15分
徳島市川内中学校:自転車35分 / 車で15分